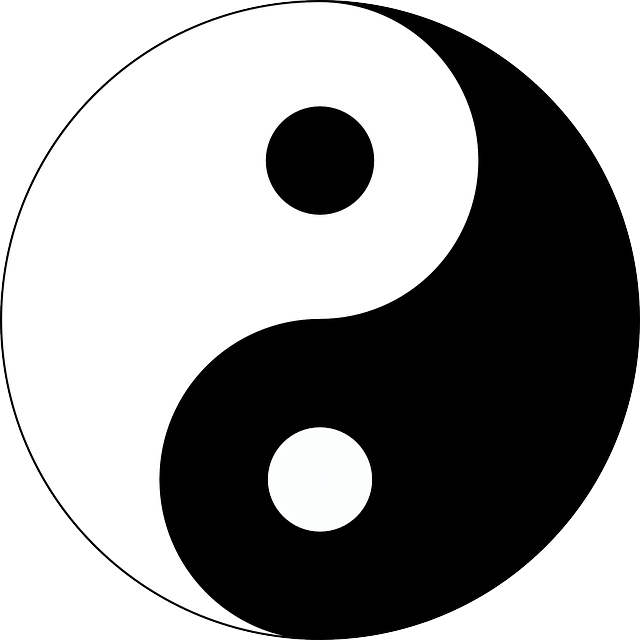禍を招く不調和の気──心身を清める秘法「陰陽道における“穢れ”の意味と浄化方法」をわかりやすく解説!
穢れ(けがれ)って言葉、なんとなく「汚れ」とか「悪いもの」って感じで使われがちですよね。でも陰陽道(おんみょうどう)の世界では、もうちょっと奥深い意味を持っているんです。
簡単に言うと「自然や人の中にある“調和の乱れ”」。つまり、目に見えないけれど、世界のバランスを乱してしまう“気”のよどみみたいなものなんですね。
このページでは、そんな陰陽道における「穢れ」の意味と、昔の人たちがどうやってそれを祓い清めてきたのかを、わかりやすくご紹介します!
|
|
|
![h3]()
陰陽道において「穢れ」とされるのは、
- 死(葬儀や死者との接触)
- 出産(血や命の境目)
- 病気(気の乱れ)
- 流血(外界との境界の破れ)
こういった日常の中の非日常なんです。これらは陰と陽のバランスが崩れるときに起こる現象とされていて、放っておくと周囲にも悪影響が広がると考えられていました。
つまり、「汚いから悪い」のではなく、世界の調和からズレている状態=「穢れ」なんですね。
![h3]()
この「穢れ」の考え方は、平安時代には国家の制度にもしっかり組み込まれていました。
たとえば『延喜式(えんぎしき)』では、
- 死者を扱った人は一定期間宮中への出入りを禁止
- 血を流した人は浄化の儀を受ける必要がある
というように、「穢れ」は社会的に管理される存在
陰陽師たちは、この「穢れ」の出入りを判断し、時には祭祀や祓いの儀式
![h3]()
じゃあ「穢れ」がついたらどうするの?ということで、陰陽道ではさまざまな浄化法
代表的なものはこちら:
- 禊(みそぎ):川や海の水で身体・心を清める儀式。神話のイザナギが黄泉帰りした際に海で禊を行ったのが起源。
- 祓(はらえ):祝詞・言霊・護符・形代(かたしろ)を使って人や場の穢れを除く。夏と冬の大祓はこの代表格。
- 結界形成:紙垂やしめ縄、五芒星、九字護身法で穢れの侵入を遮断するバリアを張る。
これらの儀式は単なるおまじないではなく、「穢れ=気の乱れを元に戻すための知恵」だったんです。
![h3]()
もう少し高度な方法として、陰陽師が行う儀礼には、
- 護摩焚き:火による清めと供養
- 鳴弦(めいげん)の儀:弓の音で邪気を断つ
- 星祭祈祷:星の運行と結びつけて穢れを除去する祭事
などもあります。これらは個人の浄化だけでなく、空間や社会全体の秩序回復を目的としていたんですね。
![h3]()
穢れの概念は、現代にもちゃんと残っています。
- 神社の手水舎:参拝前に手と口を清める
- 盛り塩:家の出入り口に置いて場を守る
- 葬式後に塩をまく:不浄を家に持ち込まないための儀礼
どれも、見えない穢れを“転移させない・ため込まない・清める”という発想が根底にあります。
つまり、穢れに対処することは、自然や人間関係、日常の安寧を守る知恵だったんですね。
五行要約
- 穢れは死・出産・病気などによる“調和の乱れ”を意味する!
- 平安時代には律令制度の中で社会的に管理されていた!
- 禊・祓・結界などで穢れを清める技術が陰陽道に伝えられている!
- 陰陽師は護摩焚きや鳴弦などの高度な儀礼で浄化を行った!
- 今でも手水・盛り塩・塩まきなどの風習に形を変えて残っている!
|
|
|