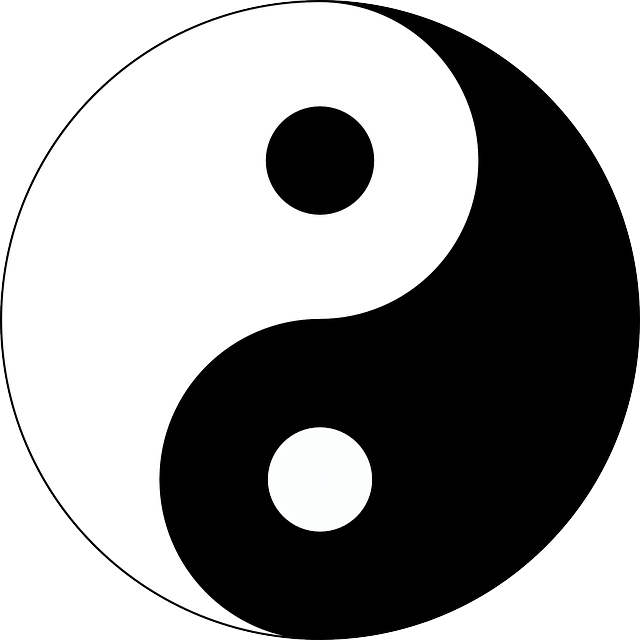陰陽道から紐解く──災厄を乗り越える節目「厄年の意味と由来」をわかりやすく解説!
厄年(やくどし)って聞くと、「災いが起きやすい年」ってイメージがあるかもしれませんが、もともとはもっと深い意味があったんです。そのルーツをたどると、やっぱり出てくるのが陰陽道(おんみょうどう)。
実はこれ、単なる迷信じゃなくて、宇宙の理(ことわり)と人の営みのバランスを読み解くための理論から生まれた発想だったんですよ。
このページではそんな「厄年」について、その意味・歴史・由来を、陰陽道的な視点からひもといていきます!
|
|
|
![h3]()
今でこそ「厄=災難の年」ってイメージが強いけど、もともとは「役年(やくどし)」と書かれていたんです。
つまり、一定の年齢に達した人が、地域や家の祭祀、神事に関わる重要な“役割”を担う年っていう考え方があったんですね。それだけ社会的責任が大きくなる時期だから、身体も精神も整えて、慎ましく過ごすようにとされていたわけです。
この「役年」が、いつの間にか「厄年」と読み替えられ、次第に「不運が起きやすい年」というふうに受け取られるようになっていきます。
![h3]()
陰陽道では、天体の動きや人の気の流れを見て、「盛りの時期」と「衰えの時期」を見極めることが大事とされてきました。
そのため、特定の年齢で運気のバイオリズムが不安定になりやすいタイミングを、あらかじめ知っておいて備える──それが厄年の目的だったんです。
また、五行の理論や九星術なども組み合わせて、より細かく「この年は危ないよ」「祈祷しておこうね」と判断していたんですよ。
![h3]()
厄年という概念が日本で具体的に文献に登場し始めたのは、平安時代のこと。
貴族たちは加持祈祷や物忌(ものいみ)を通じて、体調や家庭内の不運を避けようとしていました。『源氏物語』の中でも、厄年を意識して行動を控える描写が出てくるんですよ。
この時代にはすでに陰陽師が宮廷で活躍していて、暦や星の動きから個々人の運勢を読み解いていました。だからこそ、厄年=人生の要注意期間、という感覚が定着していったわけですね。
![h3]()
江戸時代に入ると、男性は25歳・42歳・61歳、女性は19歳・33歳・37歳など、年齢がはっきりと「厄年」として定められていきます。
とくに、
- 男性42歳:「死に(しに)」で不吉な語呂
- 女性33歳:「散々(さんざん)」で最悪のイメージ
この2つは「大厄」とされ、特に注意が必要とされてきました。
また、本厄だけでなく、前厄(その前年)と後厄(その翌年)も含めて3年ワンクールで厄払いを行うケースが増えていきます。
![h3]()
現代では、厄年を単なる「不吉な年」として恐れるよりも、人生の節目として見直す動きが強まっています。
仕事や家庭の変化が重なる時期でもあるので、
- 健康診断を受けて体を見直す
- 人生の方向性を振り返る
- 神社で厄払いして心機一転
こんなふうに「前向きなリセットのタイミング」として、厄年を活用する人も増えてるんです。
ちなみに、数え年か満年齢かについては、地域や神社によってルールが違うことがあるので、近くの神社に確認するのがベストです!
五行要約
- 厄年の起源は「役割年」で、身を慎む時期とされていた!
- 陰陽道では気の流れと暦から厄年を見定めていた!
- 平安時代の貴族たちは加持祈祷や物忌で厄を回避していた!
- 江戸時代に定番の年齢(25・42・61など)が定着!
- 現代では「人生の節目」として前向きに捉える風潮も!
|
|
|