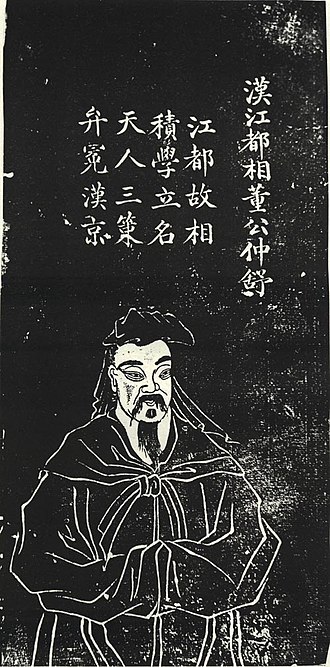恐れと祈りが交錯する異界信仰──陰陽道にみる「鬼の歴史」をわかりやすく解説!
鬼(おに)という存在、なんだか昔話や節分の中だけのキャラって思われがちですが、じつは陰陽道の世界ではれっきとした“実在する災厄の象徴”として真剣に向き合われてきた存在なんです。
特に平安時代の日本では、病、災害、怨霊…こういった見えない不幸のすべてに「鬼」が関わっているとされ、それを制御・封印する専門職が陰陽師でした。
このページでは陰陽道における鬼の歴史を、呪術・儀礼・文化の観点からわかりやすくかみ砕いて解説していきます。
|
|
|
![h3]()
陰陽道では、鬼はただの化け物ではありません。病気をもたらす疫鬼や人に憑く怨霊、さらには自然災害を引き起こす気の乱れまで、あらゆる災いの元凶とされました。
この世界観において、陰陽師は鬼=陰のエネルギーの暴走体と捉え、それを式神・呪術・結界などで祓う役割を担っていたんです。
![h3]()
鬼を祓う代表的な儀式が追儺(ついな)。これは中国の古代儀式がルーツで、平安時代には宮中で節分にあたる日に行われました。
- 陰陽師が鬼役の官人に呪文を唱えながら矢を放つ
- 豆まきの原型となった神事
- のちに民間の節分行事として広がる
つまり、節分の「鬼は外!」には、ちゃんと陰陽道の公式儀礼がベースにあったんですね。
![h3]()
平安時代は「鬼の黄金期」ともいえる時代。夜行日には百鬼が徘徊すると信じられ、貴族たちは夜の外出を避けるほど。
代表的な鬼伝説として有名なのが、
- 酒呑童子:平安京を騒がせた鬼の大将。角が五本、目が15個と描かれる怪物で、陰陽師や源頼光によって退治された。
- 鬼門封じ:北東(鬼門)の方向を忌むべき方角とし、神社や塀で対処する風習が陰陽道の地理観から始まる。
安倍晴明もまた、式神によって鬼神を制御・封印したとされ、鬼と対峙するエピソードが多数残っています。
![h3]()
平安~鎌倉時代になると、仏教の影響を受けた「地獄」のイメージが加わり、鬼は地獄の番人として描かれるようになります。
- 牛頭(ごず)・馬頭(めず)といった地獄の守護鬼
- 死後の世界における裁きと責めの象徴
このように、陰陽道における鬼は、この世とあの世をつなぐ存在として、人間の生死と深く関わっていたんです。
![h3]()
江戸時代になると、鬼は絵巻物や説話の中でキャラクター化され、「鬼退治」は娯楽としても親しまれるようになります。
でも同時に、鬼門封じの風習や護符文化として、陰陽道的な鬼への対処法もちゃんと受け継がれていました。
現代でも、
- 節分の豆まき
- 北東を避けた建築
- 厄除け札に描かれる鬼神封印の文言
こういった風習には、陰陽道的鬼対策の名残がしっかり残ってるんです。
五行要約
- 鬼は陰陽道で災厄や病の象徴とされていた!
- 追儺や節分の儀式は鬼祓いから始まった!
- 安倍晴明や源頼光が鬼退治の伝説を残した!
- 地獄観の発展で鬼は死後の守護者ともなった!
- 現代の節分や鬼門封じにも陰陽道の影響が続いている!
|
|
|