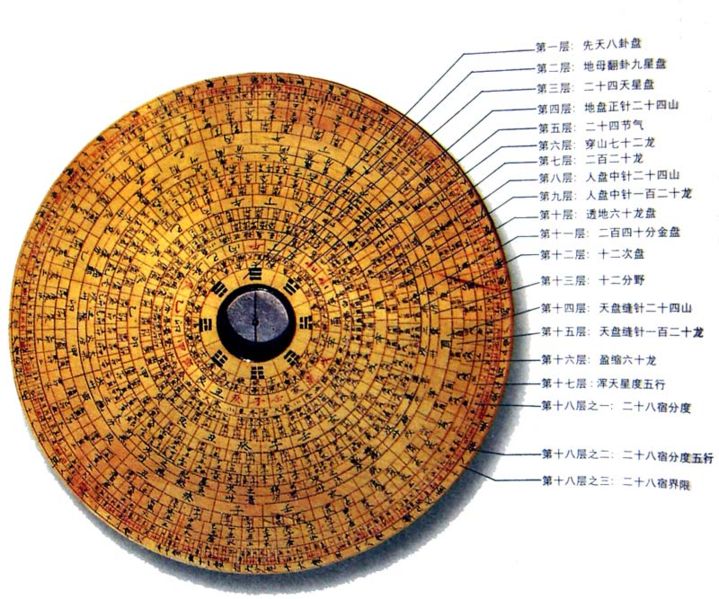本家中国との役割の違いを知る──方位と季節を司る守護神「陰陽道における“四神”信仰」をわかりやすく解説!
四神(しじん)・・・すなわち青龍・朱雀・白虎・玄武といえば、日本のゲームやアニメでもおなじみ。作品によっては悪役扱いも珍しくない神々ですが、もともとは古代中国の天文学や風水から生まれた、超まじめな方位守護の神獣たちなんです。
しかも、日本に伝わってからは陰陽道の中で独自にアレンジされて、都市計画や家相、生活の吉凶判断まで、ガッツリ日常に入り込んできました。
このページではそんな四神の意味と日本での進化のしかたを、本家中国との違いを交えながら、わかりやすくかみ砕いて解説していきます!
|
|
|
![h3]()
そもそも四神って何?というところから。
この四神は、古代中国で天を東西南北に分けたときの守護神のこと。天体の動きを七宿(しちしゅく)という星のまとまりで見て、東西南北にそれぞれ霊獣の姿をあてはめたんです。
- 青龍(東・春・木・青):商売・仕事運の象徴
- 朱雀(南・夏・火・赤):繁栄・恋愛・家族運アップ
- 白虎(西・秋・金・白):邪気除け・金運や子宝も◎
- 玄武(北・冬・水・黒):健康・長寿・守護の力
それぞれ五行・季節・色・方角の意味が込められていて、これが風水や占いの基礎にもなっています。
![h3]()
中国での四神の主な使われ方はというと、ズバリ地相と風水。特に墓地や都の設計に用いられたんです。
「四神相応(しじんそうおう)」という概念では、理想の土地の条件がはっきり決まってました:
- 東に川(青龍)
- 南に開けた土地(朱雀)
- 西に道や小道(白虎)
- 北に山(玄武)
これが揃っていると、「天地の理にかなった完璧な場所」とされていたわけです。
ちなみに、中国では中央に黄龍や麒麟を加えて「五神」とする場合もあります。
![h3]()
日本に四神が伝わると、陰陽道の世界観にがっつり取り込まれて、都市設計にまで使われるようになりました。
有名なのが平安京の四神配置!
- 青龍=賀茂川(東)
- 朱雀=正面の朱雀大路(南)
- 白虎=山陰道(西)
- 玄武=舟岡山(北)
つまり、都そのものを四神の守護の中に設計したんです。この思想は江戸や奈良、さらには地方の城下町などにも応用されていきました。
![h3]()
中国では風水の枠にとどまっていた四神ですが、日本ではもっと実践的に変化。
陰陽師たちは、家を建てる場所や神事・移転の日時などを決めるときに四神の力を取り入れ、「方除け」や「式神操作」の中でも活用していたんです。
それぞれのペアにはちゃんと意味もあって…
- 青龍⇔白虎=「不吉を祓う」力(辟不祥)
- 朱雀⇔玄武=「陰陽の調和を保つ」力(順陰陽)
このように、日本では四神が儀式や生活行動にまで入り込み、「運気の流れを整える存在」として浸透していったんです。
![h3]()
まとめると、中国と日本では四神の扱い方がまったく違うんですよね。
- 中国:天文や風水の理論として扱われ、基本は墓地や都市設計用のツール
- 日本:陰陽師が暦や儀礼、都市設計・家相まで使い倒す、信仰として民間にも広がる
特に平安期以降、日本では陰陽寮が四神を天文・地理・儀式・政治のすべてに組み込み、「日常の守護神」として定着させたのが大きな違いなんです。
五行要約
- 四神は古代中国の方位と天文に由来する神獣たち!
- 中国では風水・墓地設計に使われる地理的守護神だった!
- 日本では陰陽道を通して都市設計や儀礼に応用!
- ペアに分けて「不吉除け」「陰陽調整」の力を持つとされた!
- 生活・建築・儀式の中に根付いたことで大衆信仰へ広がった!
|
|
|