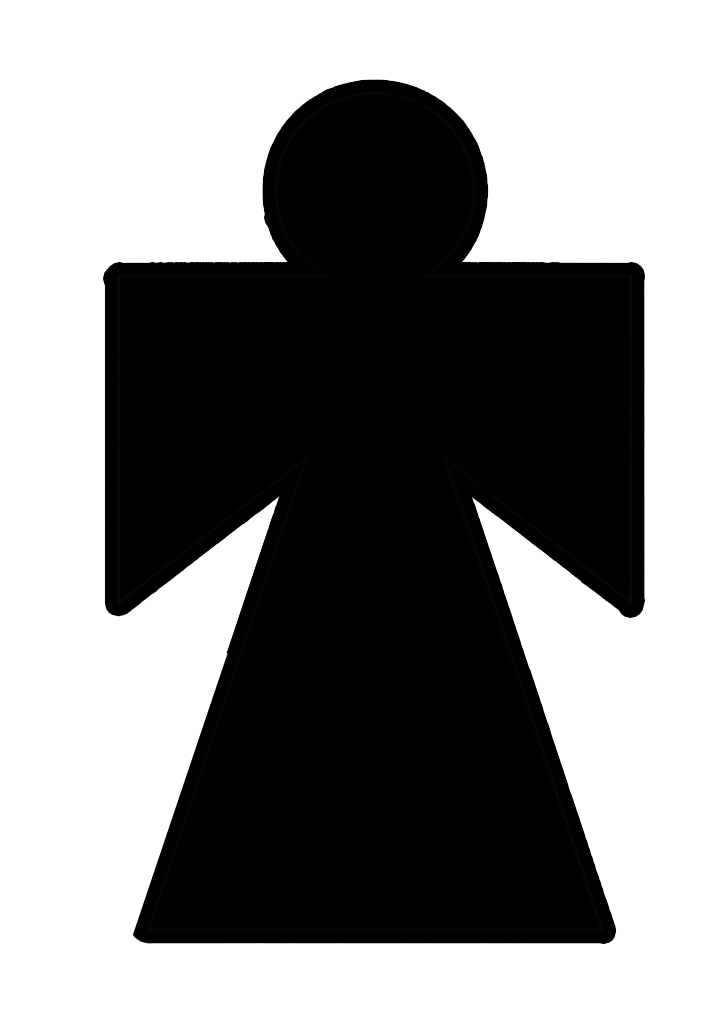陰陽師が使用する札の種類には、護符として吉凶や邪気を制するものが複数存在する。紙や木札に神名や呪文を記し、厄除け・招福・災害防止といった目的で用いるのだ。こうした御札類は陰陽道の術式において不可欠な道具であるといえる。

陰陽師の呪文とは
呪文とは、陰陽師が典礼や結界、祓いの場面で唱えた言霊や真言である。漢文や和語の語句をもって天地や鬼神に働きかけ、禍を鎮め福を招くという術理に基づいて用いられてきた。こうして呪文は単なる儀式言語ではなく、陰陽道における実践的な作用をもつ術式である。

陰陽師といえば、呪文を唱え、呪術を行ったことでも有名です。
本来呪術というのは、呪禁師が行っていた仕事で、陰陽師の仕事ではなかったのですが、奈良時代、陰陽師の吉備真備(きびのまきび)が、聖武天皇の下、それまでの「呪禁師」を廃止して「陰陽道」を採用してから、陰陽師の仕事になりました。
陰陽師が行った主な呪術は以下の通りです。
形代(かたしろ)とは、紙や土、藁などで人の形を作り、呪詛の対象にしたものです。藁人形のようなものですね。
壺などの器の中に、様々な毒持ちの虫を混在させ、共食いさせ勝ち残ったものを神霊として祀ります。そしてその毒を採取して呪詛の対象に呑ませるというものです。
『鬼門』とは、艮(うしとら/東北)の方位のことで、陰陽道では忌むべき方角とされていました。鬼が出入りする方角とされていた為です。そんな方角に結界を張るなどして、鬼の侵入を防ぐのが鬼門封じです。
式神は陰陽師が使役した鬼神のことです。その実体は陰陽師が持つ式札に封じられており、陰陽師が札に術をかけることで、自在に姿を現したといいます。そして式神を呪詛対象に憑依させ呪い殺すなんてこともできたといいます。
|
|
|